
GW明けに見られるお子さんのSOSサイン – 通信のこのこ令和7年5月号(第2号)
センター長あいさつ(藤藪庸一)
「たとえ明日世界が滅びることを知ったとしても、私は今日りんごの苗木を植える」
この言葉は、宗教改革者ルターの言葉として知られてきましたが、真相は定かではないようです。
絶望の渕に立っても、なお希望を見出そうとする力強さと、持てる力は小さくても、任されたところでベストを尽くす決意を感じさせる言葉だと私は思っています。
この言葉には「消化試合なんてない。最後まであきらめていない。最後の最後まで結果はわからない。」という意味を見出せます。
このルターの言葉と共に思い出すのは、「木を植えた男」という話です。
第一次世界大戦下でも、第二次世界大戦下でも、男は荒れた地に木を植え続け、その結果、そこに大きな森ができたという物語です。
この話はフィクションですが、私たちに大切なことを想い起こさせます。
初めは一本の木を植えることからから始めたことが、日々の積み重ねを、続けていくことで、やがて森になるということ。
毎日一本だけ植えたととしても1年で365本、三十年で一万本を超えます。
私たちの活動には、明確な終わりがありません。
ここまでやったら必要がなくなるというものでもありません。
社会を少しでも生きやすい社会にするために、目の前の人が少しでも幸せに生きられるように、私は、やっぱり今日もリンゴの木を植える。
明日も変わらずリンゴの木を植える。体が動く限り、生きている限り、リンゴの木を植える。
私はそういう人になりたいと思っています。
GW明けに見られるお子さんのSOSサイン
新年度が始まって1ヶ月が経ちましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
少しずつ新しい生活に慣れてくる頃でもありますが、4月からの緊張や疲労が心身にドッとあらわれてくる時期でもあります。
そこで、今回は、ゴールデンウイーク明けに見られるお子さんのこころのSOSのサインについて、ご家族や学校の先生方などといったお子さんの周りにいらっしゃるみなさんに、少し注意しておいていただければよいことをお示しします。
疲れや不調がでやすい5月
新年度は大人も子どもも大なり小なり何かしらの変化があります。
その変化に対応するために普段以上に緊張し、がんばり、知らないうちに疲労やストレスが蓄積していきます。
そのため、ゴールデンウィーク(GW)のタイミングで、緊張の糸が切れたかように、体調不良や気分の不安定さなどがみられることも多いです。
加えて、GW明けは大人も憂うつになるものですが、子どもも大人以上に、憂うつさや言葉ではうまく表現できないしんどさを抱えていることが少なくありません。
近頃になって、ご家庭や学校の子どもたちの様子がなんとなく気になる。
普段とは異なる様子や反応が見られる。
そのような気づきや、しんどさ・体調不良を訴えてきた場合は、『単なる怠けではないかもしれない』、『なにかしらのSOSサインかもしれない』といった視点をもって関わっていただければと思います。
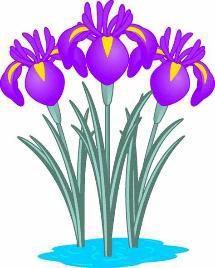
サインに気づく
例えば、今までより夜遅くまで起きていたり、朝起きてくるのが遅くなったり、起こしても布団から出ようとしなかったりしだす。
やっと起きてきても、腹痛やしんどさをさかんに訴えるようになる。
無口になったり、逆にかまってほしそうにおしゃべりが多くなったりすることもあります。
そのうち、学校や友達の話をしたがらない、ためいきが多くなったりふさぎこみがちになる。
イライラすることや、ささいなことでも泣くことが増える。
かと思うと、急に甘えてくることがある。
心配して理由を聞いたりしても、「何もない」「わからない」と応えようとしてくれなくなったりもします。
やがて、何をするにもやる気がなくなり、好きなこと、楽しいことへの興味がみられなくなったりします。
一人で抱え込まない
そんな時、お子さんの周りの皆様は、どうか抱え込まないように、相談することを心がけてください。
子どもたちを、家庭だけでなく、学校や相談機関など様々なネットワークの中で見守り、考え、関わることが、子どもたちの支えになります。
【GW中、明けに見られることが多い子どものSOSサインや症状】
・朝、起きてくるのが遅い
・腹痛や気持ち悪さなど身体症状を訴えてくる
・学校に行きたがらない、学校の話をしたがらない
・イライラすること、泣くことが増える
・急に甘えてくることがある
・やる気がなくなる、好きなこと・楽しいことへの興味がみられないなど
サインに気づいた際のポイント
◆しんどさや変化について心配している、気にしていることを伝える。
◆しんどさを言葉で表現することが難しいことも多いため、必要以上に問い詰めることがないように気をつける。
◆子どもの不安を否定せず(「気にしなくていいよ」「大丈夫」「学校に行けばなんともないよ」など)、気持ちをそのまま受け止める(「疲れるよね」「無理しなくていいからね」「してほしいことはあるかな」など)。
◆学校との連携を密にとる、相談する(担任の先生や養護教諭、話しやすい、また、お子さんが親しい先生などに)。学校での様子と家庭での様子を把握、共有し、子どもの理解を広げることが大切です。そうすることで、その子に適した関わり方が見つけやすくなります。
◆強いストレスや不安がある、身体的な不調が継続する、しんどさが分からないといった場合には、学校の先生だけでなく、スクールカウンセラーや医療機関、のこのこのような相談機関など、さまざまな面からのサポートを受けていただくことをおすすめします(受けていただきたいと思います)。
もし、サインに気づいたら、保護者・家族の皆様は、どうか、お一人で抱え込まないように、重ね重ねお願い申し上げます。
知ろう、考えよう 子どもと学校その5 「子どもの発達段階とは」④
いっしょに学びませんか
子どもの発達段階という用語に注目して4回目になります。
今回は、文部科学省のとらえ方で青年前期(中学校、12歳から15歳)について、学んでいきたいと思います。
【参考】https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/053/shiryo/attach/1282789.htm
中学生になるこの時期は、思春期に入り、親や友達と異なる自分独自の内面の世界があることに気づきはじめるとともに、自意識と客観的事実との違いに悩み、様々な葛藤の中で、自らの生き方を模索しはじめる時期です。
また、大人との関係よりも、友人関係に自らへの強い意味を見いだします。
さらに 、親に対する反抗期を迎えたり、親子のコミュニケーションが不足しがちな時期でもあり、思春期特
有の課題が現れてきます。
また、仲間同士の評価を強く意識する反面、他者との交流に消極的な傾向も見られます。性意識が高まり、異性への興味関心も高まる時期でもあります。
現在の日本の社会では、生徒指導に関する問題行動などが表出しやすいのが、思春期を迎えるこの時期の特徴であり、また、不登校の子どもの割合が増加するなどの傾向や、さらには、青年期すべてに共通する引きこもりの増加といった傾向が見られます。
これらを踏まえて、青年前期の子どもの発達において、重視すべき課題としては、以下があげられます。
◆人間としての生き方を踏まえ、自己を見つめ、向上を図るなど自己の在り方に関する思考
◆社会の一員として自立した生活を営む力の育成
◆法やきまりの意義の理解や公徳心の自覚
相談無料・秘密厳守
まずはお電話・LINE・メールでご相談ください。
必要に応じてお越しいただいたり、お伺いしてお話しすることもあります。
ささいなことでもお電話ください
9:00~17:45
TEL 0739-45-8818
LINE くまのっ子のこのこ
文章をうまく書けなくて大丈夫です。
かける範囲で書いてくださればお返事します。
E-mail nokonokojikasen@gmail.com
相談窓口(事前にご予約をお願いします)
特定非営利活動法人白浜レスキューネットワーク
くまのっ子児童家庭支援センターのこのこ
くまのっ子児童家庭支援センターのこのこ
和歌山県西牟婁郡白浜町3300-19-2F
TEL/FAX 0739-45-8818
E-mail nokonokojikasen@gmail.com
Instagram https://www.instagram.com/jikasennokonoko/?igsh=bWduOHN0dXIyOXA5
